〜Googleフォーム×Apps Scriptによる柔軟で実用的な構築例、各Stepでの記事へのリンク付き〜
はじめに:なぜ「自作」なのか?
学会や研究会の運営において、演題登録の仕組み作りは、運営の成否に関わる重要なタスクです。演題の投稿受付、修正、確認、そしてPDF出力や査読対応まで、一連の業務は煩雑であり、専用システムの導入や運営代行を検討される方も多いと思います。
一方で、次のような課題も耳にします。
- 「費用が高額で予算に見合わない」
- 「ちょっとした変更を都度依頼するのが大変」
- 「投稿件数が限られている小規模研究会では過剰なシステムに感じる」
こうしたニーズに応える方法として、**GoogleフォームとApps Scriptを用いた「自作システム」**があります。
本記事では、当ブログで連載してきた自作手法の全体像をまとめるとともに、既存の選択肢との比較、構築にあたっての注意点や導入のヒントをご紹介します。
学会演題登録システムの選択肢とその比較
選択肢①:運営代行会社への委託
運営会社に演題登録から抄録集作成、現地運営まで一括して依頼するスタイルです。大規模学会では主流の手法であり、信頼性・対応力の面では安心感があります。
ただしデメリットとしては、
- 費用が高額になる(数十万〜数百万円単位)
- 一部の仕様変更には時間や追加費用がかかる
- カスタマイズ性に限界がある
といった点があります。
選択肢②:UMINの演題登録システムを活用する
大学・病院等で広く活用されているUMIN(University Hospital Medical Information Network)の演題登録システムは、信頼性の高い公共サービスとして広く知られています。
🔗 UMIN公式案内ページ(演題登録)
👉 当ブログでの紹介記事はこちら
メリットとしては、
- 安価で利用可能
- 投稿〜修正〜査読〜採択の一連管理が可能
- 学会向けに最適化された入力構造とテンプレートがある
- カスタマイズや自由な項目追加の相談が可能
一方で、
- 実際に演題登録が開始されるよりも数か月前に申請などが必要
など、もしかしたら状況と会わない場合もあるかもしれません。
選択肢③:Googleフォーム×Apps Script による自作
Googleフォームを窓口にし、Apps Scriptで演題番号の自動付与、PDF整形、メール送信などを連携させることで、非常に柔軟な自作システムを構築できます。
特に以下のような学会・研究会に最適です:
- 年間1回〜数回程度の開催で演題件数が20〜200件規模
- カスタマイズした入力項目を使いたい
- 原稿フォーマットやファイル名に独自ルールがある
- 手作業を極力減らし、ヒューマンエラーを防ぎたい
自作システム構築の全体像(記事連携)
以下の順序で構築すれば、フォーム作成〜演題番号付与〜PDF出力〜メール送信〜全自動化まで実現可能です。
Step 1:フォームの作成と設計
所属、氏名、演題名、抄録本文などの基本項目
- 必須チェック、文字数制限、段落型入力の活用
- 複数所属・筆頭演者フラグの設計方法も紹介
Step 2:受付番号の自動付与
- 「0001」「0002」形式で自動連番:設定次第で変更可能
- 演題修正時の重複防止ロジックも対応
Step 3:Googleドキュメントで抄録を整形
- 氏名・所属・抄録内容などを希望の形に並び替えてドキュメントやPDFとして自動出力
- 複数演者の整形と演題番号の見出し設定
- PDFファイル名に演題番号を反映も可能
Step 4:メールでPDFを自動送信
- 入力者への確認メール送信
- PDFで登録した演題内容を送信でき、内容の確認にもつながる
- グーグルフォームから修正することで、内容のアップデートがいつでも、自動的に可能
- 送信履歴もスプレッドシートに記録
Step 5:全自動化トリガー設定
- フォーム送信と同時に全処理を起動
- 管理者の手間ゼロで完結
Step 6:複数フォーム統合・参加登録・リセットなど
- 日本語・英語フォーム等複数のフォームからの内容を統合管理
👉 複数フォームの統合方法 - 事前参加登録の実装例
👉 受付フォーム構築例 - フォームの初期化・再利用
👉 フォームリセット方法
自作運用のメリットと注意点+実践的対策
自作の利点
- コストゼロ(完全無料)
- 設問・フォーマットの自由設計
- 修正・再出力も柔軟対応
- Google Drive上で安全に一括管理可能
- フォームデータがリアルタイム反映
⚠ 注意点とその対処法
| 課題 | 実践的対策 |
|---|---|
| Apps Scriptの実行制限(Quota) | メール送信は1日100件が目安。 → イベントを分散、管理者メール送信と併用。 |
| フォームの公開範囲制限 | URLを知っている全員がアクセス可能。 → 招待制/承認制にする、内部コードを入力必須に設定。 |
| 情報保護・データ管理責任 | 氏名・所属・メールが個人情報に該当。 → 最小限の取得+アクセス制限。必要に応じてPDFをパスワード付きに。 |
| スクリプトの可読性と保守性 | 複数人で運用するなら、関数の分離・変数名の工夫・コメント付けが必須。 → バージョン履歴の利用とドキュメント化を推奨。 |
まとめ:自作システムは“現実的で実用的”な選択肢
GoogleフォームとApps Scriptを活用することで、演題登録に求められる機能を自前で構築することが十分に可能であることが、本ブログで紹介してきた一連の記事からご理解いただけたかと思います。
- 実際に動かせるコードが付いている
- 各ステップで「よくあるつまずき」への対処法を記載
- 素人でも試行錯誤しながら完成できるよう段階的に構成
という点で、再現性と実用性を重視した構成になっています。
「最初は大変そうに見えたけど、この手順通りに進めたら動いた」という声も多く、特に初めて学会を主催する方には多くのメリットがある内容です。
❓お問い合わせ・ご質問はこちら
ご質問や「ここがうまくいかない」「この点はどのように解決したのか」等といったご質問があれば、ぜひお気軽にご連絡ください。
私の解答可能な範囲で、お答えいたします。

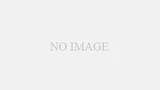
コメント